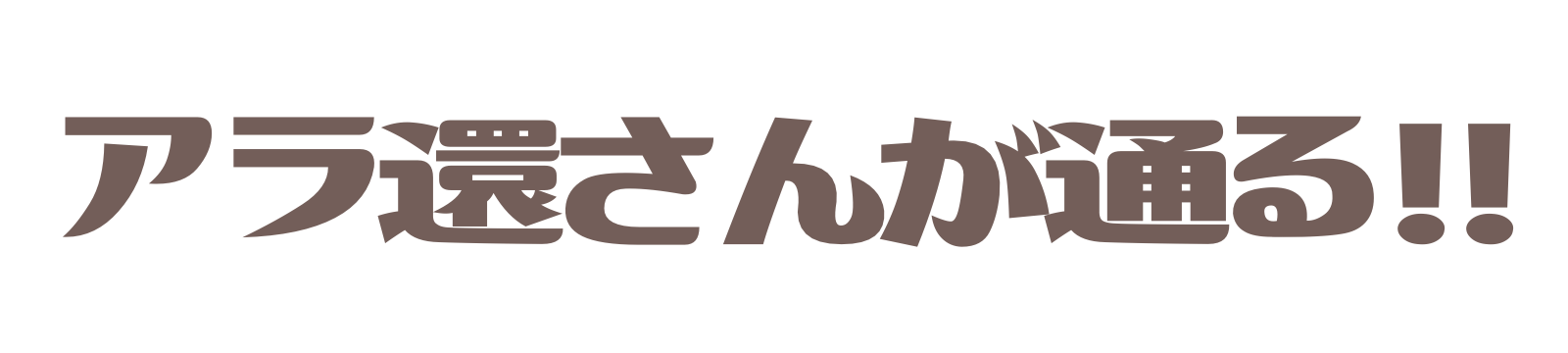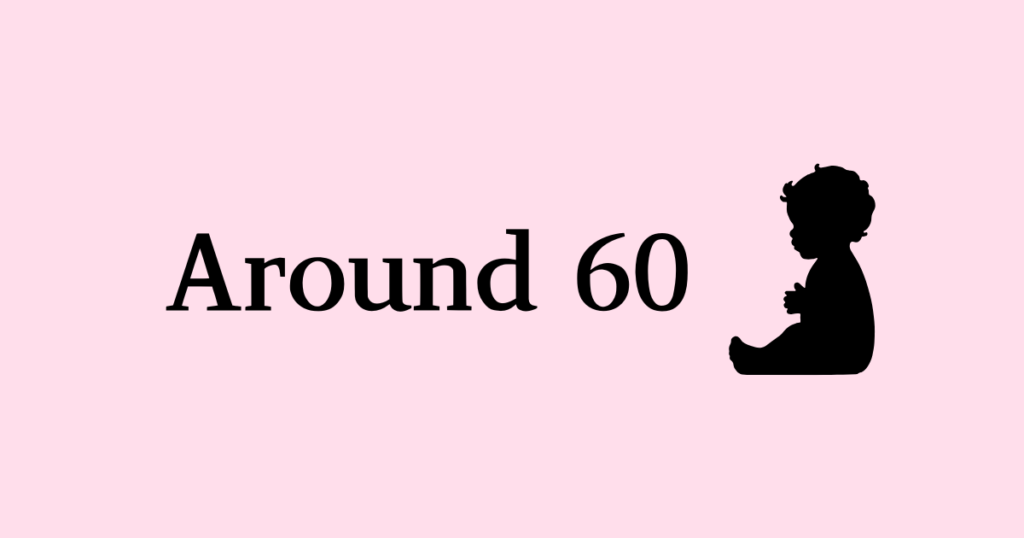
子育てに全力を注いできた親にとって、子どもが自立していく過程はうれしくもあると同時に寂しさも伴うものです。
とくに思春期を迎えた子どもが親から少しずつ距離を置くようになると、「もう子どもじゃないのね…」と実感する場面が増えていきます。
ところが、いつまでたっても子離れできない親は少なくありません。
たしかに、私たち親世代の多くが、子育てを人生の中心として全力で走ってきたからこそ、「役目が終わる」ことへの戸惑いや不安を感じるのは当然です。
でも、子どもたちは確実に自分の道を歩みはじめています!
もしその変化に気づかず、子離れができないままでいたら…
子どもとの関係や自分の人生に、どのような影響が出てくるのでしょう?
今回は、子離れの重要性と、できなかった場合に起こりうるリスクについて、考えてみましょう。
私自身の“子離れ”の現在地

じつは私自身も、子どもが遠方の大学に通っているため、すでに「子離れ」の入り口には立っています。
毎日顔を合わせるわけではなくなった今、ふとしたときに寂しさを感じることも…。
それでもまだ、完全に独り立ちしたわけではありませんから、きっと将来、結婚や本当の意味での自立を迎える時には、また違った種類の寂しさがやってくるのでしょう。
その時こそが本当の「子離れ」のタイミングかもしれません。
でも、親としての私の役目は、我が子を信じて送り出すこと。
そして、未来の結婚相手や家族との関係においても、健やかにバトンを渡すことが、親としての務めだと思っています。
子どもの幸せを願うなら、そのパートナーとの関係も大切にする覚悟が必要なのだと、少しずつ心の準備をしているところです
子離れできない親の特徴とは?
子離れができない親にはいくつかの共通点があります。本人は「愛情」だと思っていても、周囲から見ると“過干渉”に映ることも。

❶ 子どもの生活に過干渉する
LINEや電話を頻繁にし、子どもの交友関係や予定に口を出すなど、プライベートな領域に立ち入りすぎてしまう。
❷ 子どもを通じて自分の生きがいを感じている
自分の趣味や人生の楽しみがなく、子どもが生きがいの中心になってしまっている。
❸ 子どもの決断に過度に口を出す
進学や就職、恋愛や結婚など、子どもが自分で選びたいと思うことにも「こうすべき」と指図してしまう。
❹ SNSや連絡を頻繁に求める
毎日連絡がないと不安になり、既読スルーにも過敏になる。もはや、子どもを「管理」してしまう傾向に。
子離れできない親が迎える末路

❶ 子どもとの関係が悪化する
「親の干渉が重い」と感じた子どもは、次第に心の距離を置くようになります。連絡頻度も減り、最悪の場合は疎遠になってしまうことも。
❷ 子どもの自立が遅れる
失敗する経験も成長の一部。親がすべてを先回りしてしまうと、子どもは自分で考え判断する力を養えません。その結果、社会に出てから苦労することになってしまいます。
❸ 親自身が孤独に陥る
「子ども中心」の人生を送ってきた場合、子どもが家を離れた後に “空の巣症候群” のような喪失感に襲われることも。趣味も人間関係もなく、孤独になってしまうケースは少なくありません。
❹ 子どもの結婚・家庭に悪影響を及ぼす
子どもが結婚してからも過干渉を続けると、配偶者との関係に溝ができたり、家庭内にストレスが生じたりします。最悪の場合、離婚の原因になることも…!
子離れを成功させるためにできること
子離れとは、「愛を手放すこと」ではありません。「信じて任せること」なのです。では、どうすれば上手に子離れできるのでしょうか?

❶ 親自身の人生を豊かにする
子どもが巣立ったあと、自分の時間が増えるのは大きなチャンス! 旅行に行く、習い事を始める、友人と再会するなど、「自分のための人生」を楽しむことが、子どもにとっても安心材料になります。
❷ 新しい人間関係を築く
趣味の仲間、昔の友人など、また、新たな人間関係を築いておくと、子どもへの依存度が下がります。自分の世界を持っている親は、子どもにとっても頼もしい存在です。
❸ 子どもを信じて任せる勇気を持つ
親が心配しすぎると、子どもも不安になります。「きっと大丈夫」と信じることが、子どもに自信を与える最大のサポートです。
子離れは「親の卒業式」でもある

子育てのゴールは「親のもとを離れて、幸せに生きていける大人にすること」。
親の手を離れてこそ、子どもは本当の意味で “羽ばたく” ことができます。
親にとっても、子離れは新たなスタートです。
寂しさを否定する必要はありません。
でも、それを成長と喜びに変えていけたら、きっと親子の絆はもっと強く、深くなります。
最後に … | 信じて見守るのも愛です

子離れができないことは、決して “ダメな親” の証ではありません。
それだけ子どもを愛してきた証拠ともいえるのです。
でも、だからこそ最後には、「信じて見守る」という愛のかたちにシフトしていく必要があります。
「私も寂しい。でも、子どもの人生を応援したい」
そんな親心こそが、子どもにとって一番の力になるのだと思います。
子どもの幸せな未来のために、そして自分自身の未来のために。
「子離れ」の準備は、少~しずつ、前向きにはじめていきましょう