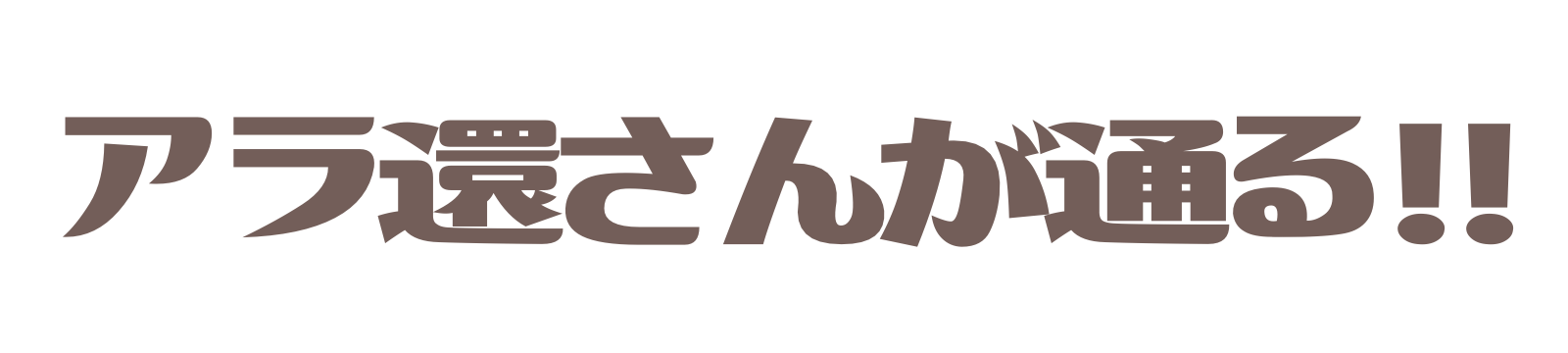アラカン世代の私が幼い頃、まだバレンタインデーという習慣は今ほど広く浸透していませんでした。
幼稚園児だったある日、兄が素敵なハート型のチョコレートをもらっているのを見て、私は「どうして私にはないの?」と尋ねました。
すると母が、「今日はバレンタインデーといって、男の子にチョコレートをあげる日なのよ」と教えてくれたのが最初の記憶です。
それから、私の成長とともに変化していったこのイベント。
今回は「ヴァレンタインデー」でなく、敢えて昭和時代の「バレンタインデー」を思い出してみることにしましょう
バレンタインデーのチョコレート文化は昭和から始まった!

バレンタインデーのはじまり
このイベントが日本に初めて紹介されたのは、昭和30年代(1950年代後半)頃のこと。
洋菓子メーカーが販促キャンペーンとして取り入れたのがはじまりで、当初は欧米のように恋人同士がプレゼントを贈り合う日として宣伝されていました。
しかし、なぜか日本では徐々に「女性が好きな男性にチョコを贈る日」として独自の文化が形成されていったのです。
欧米をはじめとする多くの国々では、バレンタインデーは恋人同士や夫婦が愛を祝う日として認識されています。この日はお互いに贈り物を交換したり、一緒に特別な時間を過ごしたりするのが一般的です。花束やカード、チョコレートが人気のギフトですが、贈り手が女性に限られるわけではなく、男性から女性に贈ることも普通です。
また、友人や家族と気軽にカードを贈り合う文化がある国もあります。アメリカでは子どもたちが学校でクラスメート全員にバレンタインカードを配る習慣があります。こうしたカジュアルな形態のバレンタインは、日本のように特定の誰かに思いを伝えるイベントというより、より広い意味での愛情や感謝を共有する日とされています。
バレンタインデーの定着
70年代の終わりから80年代にかけて、バレンタインデーは次第に「女の子が好きな男の子にチョコをあげる日」として浸透しはじめました。
当時、小中学生だった私たちは、友達と計画を立てたり、放課後に作戦会議をしたり・・・。
バレンタインデーはかなり盛り上がる一大イベントだったのです!

昭和の学生 バレンタインあるある!
昭和時代、バレンタインデーはドキドキとワクワクが詰まった特別な一日でした。ここで、昭和の学生たちが経験したチョコレートを巡る様々なエピソードや、当時ならではの習慣、「バレンタインあるある」を振り返ってみましょう!
1. 好きな子の机にそっとチョコを忍ばせる!
学校で直接渡すのが恥ずかしくて、好きな男の子の机の中や下駄箱にそっとチョコを入れるのが定番でした。放課後、見つけた本人が喜んでくれる姿を想像して、渡す側もドキドキ なぜか名前を書かかない、はずかしがり屋の女子もいましたが、それは意味がないのでは?と大人になった今は思います・・・。
2. 学校のアイドルにチョコが殺到!
学校中の女子たちから憧れられるアイドル的存在の男子には、大量のチョコが集まりました。下駄箱や机がチョコで埋まっている光景に、羨望とちょっぴりの嫉妬が入り混じる瞬間も。 ・・・果たして本人に食べてもらえたのでしょうか?
3. 放課後の直接告白!
中には、放課後に好きな男の子を呼び出して直接告白する勇敢な女子も! 成功して両思いになればいいのですが、お節介女子が振られてしまった子を慰めたりしているのも定番の光景でした。 中には「○○君、ひどいわよ!」と正義感で詰め寄る女子もいたりして。
4.現役のアイドルにも郵送!
昭和時代はファンレターを送る習慣があったので、バレンタインデーは好きなアイドルに本気のチョコレートを送る人、中には追っかけをして渡す人もいました。 私の頃は「たのきんトリオ」や「シブがき隊」などが人気で、トラック何台分ものチョコレートが届いたそう。

たぶん食べてもらえないのに・・・
5. 手作りチョコで愛情表現!
「手作りの方が気持ちが伝わる」と、家で一生懸命チョコやクッキーを作る女子も多くいました。 でも、当時はお菓子作りに不慣れな女子が多く、じつは「売ってるチョコのほうがうまい!」という男子の本音も聞かれました。
6. 義理チョコのはじまり!
まだ「義理チョコ」という言葉はなかったかもしれませんが、仲の良い男友達に「これ義理だから!」と念を押して渡す女子も増えていきました。 気軽に渡しているつもりでも、受け取ったピュアな男子はつい「これは本命かも」と期待してしまうことも。



義理の場合、不二家のピーナッツ入りのハートチョコとか!
7. 男子の間での盛り上がり!
バレンタインデーは女子だけのイベントではありません。男子たちも「何個もらった」と報告し合ったり、自慢し合う場面がよく見られました。 中には「今年はゼロ…」としょんぼりする子も。 「もらったけど、お母さんから。」というパターンもありましたね!
8. 学校でバレンタイン禁止令!
あまりにも盛り上がりすぎて、一部の学校では「バレンタインデーにチョコを持ってくるのは禁止!」というルールができることも。 放課後、隠し持っていたチョコを待ち伏せして渡す女子たちもいました。
9. ホワイトデーの期待!
いつの間にか、両思いなら一ヶ月後にマシュマロを返すという習慣も生まれました。 女子は一ヶ月ドキドキして過ごしたものです。 後に「ホワイトデー」と呼ばれるようになったその日は、両思いでなくてもきちんとみんなにお返しをようになったり、お菓子もマシュマロに限らなくなったり、いろいろと形を変えていきました。


バレンタインデーの進化
1980年代後半から1990年代初頭のバブル期、日本のバレンタインデー文化は大きな変化と豪華さを伴って進化しました。 経済の勢いとともに、恋愛やプレゼントのあり方も贅沢で派手になった時期です。
バブル期のバレンタインデーの特徴
1. 高級チョコレートが大流行!
バブル期には、高級チョコレートがバレンタインの主役になりました。 従来の市販のチョコや手作りチョコに加え、有名ブランドの高級チョコが大人気! ゴディバなどの海外ブランドも注目を集め、百貨店の特設コーナーは女性たちで溢れかえりました。この時代の女性たちは、高級感溢れるセンスのよいチョコを選ぶことも、自分が特別であるように感じていたのかもしれません。
3. 贅沢なバレンタインデート!
なぜかバレンタインデーもクリスマスイブのように、ちょっとゴージャスなディナーを楽しんだり、素敵なデートをする日になっていきました。 告白するだけでなく、恋人同士が楽しく過ごす日になったという感じ?
3. プレゼントの多様化!
バブル期は「チョコだけでは物足りない!」という風潮もありました。 男性へのプレゼントとして、高級ブランドのネクタイや財布、アクセサリーなども人気になり、女性たちはチョコと一緒に贈る品物選びに頭を悩ませていました。



その分、ホワイトデーのお返しも高価な物が!
バブル期のバレンタインの影響
バブル期の華やかさは、バレンタインデーにも強く反映されました。
「とにかく派手に、贅沢に」という時代背景の中で、この日はただのイベントではなく、大人の女性たちのステータスやセンスを見せる場となっていました。
現在では少し落ち着いた印象のあるバレンタインデーですが、好きな人への告白や、親しい人へのプレゼントだけでなく、高価なチョコを自分へのご褒美にする人も増えています。
世界中の贅沢なチョコレートに関心が寄せられはじめ、その味を楽しめるようになったのもバブル時代があったおかげなのかもしれませんね。


昭和のバレンタインデーを懐かしむ
昭和時代は、バレンタインデーの浸透から定着、そして進化を遂げる過程を目の当たりにする時代でもありました。
学生だった頃の甘酸っぱい思い出や、友達同士でのドキドキの共有、そして大人になるにつれてのチョコ選びの楽しさ・・・。
形は変化しても、バレンタインデーが私たちにとって特別なイベントだったのは確かです。
令和の今では、ジェンダーに関係なくチョコを贈り合う文化や、「友チョコ」「自分チョコ」など新しいスタイルも生まれています。



多様性の時代ですね~。
ただ、昭和の学生のバレンタインは、特有の純粋さ不器用さがあり、ちょっとした勇気が必要なイベントだったように思います。
バレンタインデーはまだまだ進化していきそうですが、せっかくのこの時期、皆様もぜひ美味しいチョコレートを楽しんでみてはいかがでしょう?